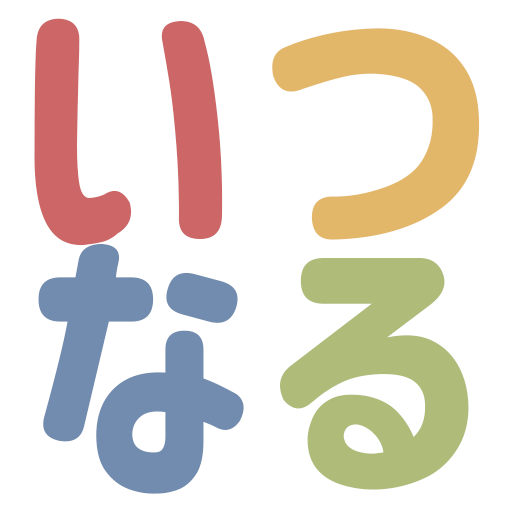ドレンチャー設備の役割
最初の記事からどうぞ。

ドレンチャーヘッドという部分から水が出るんです。
何のためにか・・・?。
隣からの火災の延焼から守るためですっ!。
例えるなら、新世紀エヴァンゲリオンの「ATフィールド」。
いやいや、エヴァはあまり詳しくないのに書いてしまった(笑)。
建物の水幕のバリアって感じですね。

・・・まっ、建築士試験的には、説明はこれだけで終わってしまうんですけどねっ。
先日、友達がランチをしている時にテーブルの横にあったものを写真を撮ってきて送ってきてくれたんです。

「ドレンチャー設備」の操作ボックスって書いてあるんやんっ!。
こんなん押したら、ATフィールドがかかってまうやん~っ!。
押してしまうとどんなことになるのか・・・(汗)。
ドレンチャー設備のデモストレーションの動画を見つけたので、URLを載せておきますね。
参考動画☞ドレンチャーのデモストレーション
この動画を見ていると、「ふ~ん、なるほどねぇ~」って言う感じなんですが、途中で・・・。
「おぉ~!」っとなってしまいました(笑)。

ドレンチャーのインパクトが強すぎてもう忘れらない・・・(笑)。
ドレンチャー設備って、重要文化財の寺社仏閣にも利用されたり、また劇場の舞台と客席にも使われるらしいです。
では、ここで問題を1問っ。
一級建築士試験の平成25年度の問題より
ドレンチャー設備は、外部等からの延焼を防止するため、ドレンチャーヘッドから放水し、水幕をつくる消火設備であり、重要文化財の神社や仏閣等に使用されている。
あと、二級建築士では「ドレンチャ」が「衛生器具設備」だという組み合わせの問題もありましたが、消火と言うより・・・防火設備になりますので、誤りで出題されていたことがあります。
あと、もうひとつカッコイイなぁ~っと思ったのが、「可動式の放水型スプリンクラー設備」。
「放水型スプリンクラー設備」は、可動式と固定式があるのですが、どちらも高い天井で儲けられるもの。
その中でも「可動式」がカッコイイんです。
って、スプリンクラー設備を使う時って、火災が起きた時なんでカッコイイとか言ってたらダメなんですけどね。
また、こちらも百聞は一見に如かず。
どんなんか、見てみるとこちらも忘れられないかもよっ(笑)。

参考動画☞放水型スプリンクラー設備
なかなか見る機会がないからこういう動画があるとすごく勉強になりますっ。
消防法では、高い天井の建築物・・・10mを超えるくらい(物販等だったら6m)の高い天井のところには「放水型スプリンクラー設備」をつけましょうと定められています。
法規の試験でもそこまで出ないけど、まぁ、それだけ高い天井のところにつけるということ。
では、問題を1問っ。
一級建築士試験の平成29年度の問題より
スプリンクラー設備の設置が必要なホテルにおいて、床面から天井までの高さが12mのロビーに、放水型ヘッドを使用したスプリンクラー設備を設置した。
まとめ
ドレンチャー設備なのですが、消防用設備等での種類でいうと、消火設備は、住んでいる人たちや関係者たちが自分達で消火活動するための設備なので、違うし・・・。

実はドレンチャーは、消防法で明確にされている訳ではなく、建築基準法第2条九の二ロに「防火戸その他の政令で定める防火設備」となっていて、その政令の施行令第109条の「防火戸その他の防火設備」の第1項に「ドレンチャー」があるんで、さきほどの二級建築士の問題のところで「防火設備」と書いていたんです。
スプリンクラー設備もドレンチャー設備も同じ「水」を使っているのに「消火設備」と「防火設備」になっているのが何となく知っておいてもいいかと思って。